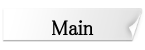縁の糸 4 —— リクオ 嫁取り物語 ——
1
「さぁ、着いた。行くよ」
リクオは車を駐車場に止めるとパーキングブレーキペダルを踏み込んだ。
雪女と鴆が車から降りるのを確認してからリクオも車から降り、キーをかける。
「ご立派な建物ですね、若!」
「ハハ…そうだね」
此処は、リクオが通う大学。
そして今日はその学園祭。雪女がどうしても行ってみたいと強請った為、こうなった。
「…にしても鴆様、とってもお似合いです、洋装!」
白地に水玉模様のチュニックブラウスにジーンズという装いにデニム地のパンプスで二人の前を歩く雪女が振り向き様に鴆に笑顔を向ける。何処から見ても女子大生だ。
「ホント、ボクの服が合って良かったよ」
黒の七分Tシャツにオリーブのカーゴパンツ、そして足下はスニーカーといったラフなスタイルのリクオが目尻を下げて笑った。
「…なんでオレまでこんな所に来なくっちゃならなねぇんだ…」
黒のシャツに白のネクタイを付けて黒のスーツ——といっても暑いので上は脱いでしまい肩にひっかけているが——に身を包んだ鴆は、ポツリと愚痴った。
全身黒尽くめの鴆は、それはそれは本当にヤクザらしく見えた。
鴆は当然乍ら洋服など持っている訳もなく、だからといっていくらなんでも晒に着流し姿で来させる訳にもいかない。
リクオは慌てて自分の服を見繕って着せてみたのだが、いい具合に大きさはなんとか合った様だった。
昔は鴆をいつも見上げていた。
昼の姿のときは勿論、夜の姿のときもほんの少しその背は及ばず。
それがいつしか夜の姿のときだけは視線が並ぶ様になり…そして今、昼の姿のときも視線が並ぶ様になり、体格そのものはリクオの方が上回っている。
「いいじゃないか、たまには」
「よかねぇだろ」
「え、なんで?」
キョトンとするリクオに鴆は苦虫を噛み潰した様な顔を向けた。嫌いなのだ、こういった場所が。
そんな鴆にリクオは小さく笑ってゴメンゴメンと謝る。
「…雪女と二人じゃ、話に困るし…」
「だからってお前…」
「義兄弟だろ、助けてよ」
そして三人は大学の構内へと入って行った。
数々の模擬店に瞳を輝かせる雪女に男二人は振り回される。やれやれと鴆が溜め息を付けばリクオは笑う。
「…可愛いよね、雪女…」
独り言の様にポツリと言う。
「…ちっとも変わらない…」
「あぁ、オレたち妖は変わらねぇ。変わってゆくのは人間達だ …」
そう言ってちらりリクオを見やる鴆。
「…そっか。変わってしまったのはボクの方か…」
「二人とも早くー!」
向こうで雪女が手を振っている。今行く、とリクオは笑顔で返して鴆を促した。
「済みません、鴆様、お疲れになられました?」
「…ちぃとばかし、な」
「雪女、ボクたちは此処で休んでるから、模擬店、見て回るといいよ」
ベンチに鴆を座らせ乍らリクオは言った。
「…はい…でも…。あ、何か飲み物買ってきましょうか?何が宜しいですか?」
雪女の言葉に、リクオはじゃ…と財布から札を取り出し手渡した。
「雪女の好きなものを買って来て。ボクはそれでいいから」
鴆もそれでいいよね、と有無を言わせず従わせる。
畏まりました、と雪女は言うが早いか駆けて行く。
「…やっぱり可愛いよね、雪女」
リクオもベンチに腰をかける。
「…じゃ、雪女を嫁にするかい?」
何気無さそうに鴆は言ってのけた。
しかし、これは何気に言った訳ではない。いつだったか初代総大将•ぬらりひょんに問われた事があるからだ。
初代はリクオの嫁取りを気にしている。本当の所リクオ自身はどうなのか、何気無さを装い水を向けてみたのだ。
「…それは、無いなぁ…」
一呼吸おいてリクオは小さく答えた。
「なんでだ?じゃ、あの陰陽師の嬢ちゃんか?」
まさか、と笑うリクオは、あ…そうだ、鴆に向き直った。
「思い出したよ、鴆」
「何を?」
「ほら、いつだったか本を返してくれって言われてたろう?あれ…実はまだ返してないんだ…」
気まずそうに言うリクオに鴆は首を傾げた。
「何で?」
「何で…って…」
「連絡の取り様が無ぇのか?」
「…いや、そうじゃなくって…」
「じゃなんだ?」
「…なんか、連絡し辛くって…ついつい…」
「なんで?」
「…なんで…って、その…」
——夜の奴良くんはやっぱりなんか苦手や——
面と向かって『苦手』と言われたのである。それが『夜』限定であったとしてもだ。
自分の事を苦手と言ったのだ、彼女は。
「そ、そうだ、鴆が連絡取ればいいじゃないか。連絡先は教えるよ。そもそも彼女は鴆にあれを持って来たんだし——」
リクオがそこまで言った時、リクオの背中で声がした。
「お待たせしましたー!…って、どうされました、鴆様?」
雪女の顔からふと笑顔か消える。
見れば鴆の眉間には深く深く皺が刻まれている。何かあったのだろうか、はたまたすこぶる体調が悪いのだろうか。
「…いや、なんでもねぇ。済まなかったな、雪女」
雪女からストローの刺さった飲み物のカップを受け取り乍ら、鴆は答えた。しかし、相変わらず眉間には皺が刻まれている。
失礼します、そういって雪女は鴆の眉間に指を添えてピッと引っ張った。
「男前が台無しですわ、鴆様」
雪女は笑った。
2
「なんの話をされていたのです?」
雪女もベンチに腰をかけて、買って来たグレープフルーツジュースを飲み乍ら二人に問う。
「なんでも——」
無い、と言いかけた鴆をリクオが遮った。
「花開院さんの事を話してたんだよ」
「花開院…?あの、陰陽師娘の事ですか?」
雪女の問いにリクオはストローを啣え乍ら頷いてみせた。そして、話して聞かせる。以前、彼女が鴆にと持って来た風呂敷包みの一部始終を。
そんな事があったんですか…。ポツリと呟き乍ら雪女は、あの日の事を思い返した。花開院ゆらが訪れた日の事は覚えてはいるが、鴆との間にその様なやり取りがあったとは。
何やら物思いに耽る様な雪女にリクオは続ける。
「もしかしたら…彼女は鴆が好きなんじゃないのかな?」
「「え!?」」
リクオの言葉に鴆と雪女はギョッとする。ストローを口から外してポカンとする雪女、そして鴆は飲み物のカップそのものを手から落としそうになっていた。
「…だって…そうでなきゃ、わざわざ京都からあんな薬の本抱えてくる訳が無いよ」
「三代目襲名の祝いのついで、だろ?」
口元を引きつらせる鴆。
「そっちがついでだったんだ。大事なのはあの本を鴆に渡す事だったんだよ」
大体、三代目襲名から日が経ち過ぎる。あれは、口実だったのだ。
それに…彼女が鴆のどこに惹かれたのか知らないが、わざわざ十冊もの本を抱えてやってくるのだ、そこにはそれなりの思いがあったに違いない。
現にその本のお陰で鴆は随分良くなった。床に伏せる事も少なくなったし、吐血の回数と量もかなり減っている。
鴆の体内に宿る鴆毒が彼女のもたらされた薬の本に書かれたなにかによって中和されているのだろう。
決して消し去る事の出来ない鴆毒ではあるが、ただ蝕まれ耐えていた日々を思えば随分と未来は明るくなった。
「ぜ、鴆様!いけませんわ!あんな陰陽師娘など!滅せられますよ!封印されちゃいますよ!」
「……。…なに言ってやがる、雪女…」
オレがあの陰陽師の嬢ちゃんとどうにかなるとでも思っていやがるのか?鴆はまた眉間に皺を寄せた。
「で、鴆は…どうなの?」
「え?」
どうなの、と聞かれて、何が?と聞き返そうになってしまう。
「彼女は確かに陰陽師だけど、無闇に滅したりしないよ。ボクたちの事も充分理解してくれてるじゃないか。それに——」
リクオは一旦言葉を切った。
「それに、いつまた彼らと共同戦線を張らなきゃならなくなるかもしれない。仲良くする事は悪くないとボクは思ってるんだけど。ね、鴆?」
——『ね、鴆?』って…えぇっ!?——
話がえらい方向にいってしまっていた。これはどうしたものか。このままでは自分があの陰陽師の人間とどうにかさせられてしまいそうだ。
鴆はジュースを一気に飲み干すと、空になったカップを傍に合ったゴミ箱へと投げた。そして恭しく立ち上がる。
「…ちと先に帰るわ。お前たち、まだ回るんだろ?」
「え…帰るの、鴆?」
「…あ、いや…一人で帰れるからな、気にすんな」
立ち上がりかけたリクオを鴆は制した。
「…一人で帰るって…どうやって…」
鴆はこの街の交通事情には疎い。一人で歩かせたならば迷子になるのは必至だろう。一人で帰らせるわけにはいかなかった。
けれど。
鴆はニヤリと笑って、空をついと指差した。
「え?」
リクオと雪女は同時に空を見上げる。
「飛んで帰る」
言うが早いか鴆はタン!と地面を蹴った。黒の洋装に身を包んだその姿は、あっという間に鳥の姿へと変化を遂げる。バサバサッと大きな羽音をたてて鳥は大空へと舞い上がって行った。蒼とも翠とも言えぬ美しい色をした鳥は、見る見る空の彼方へその姿を小さくしていった。
「鴆様…飛んでいかれましたね…」
「…そう…だね…」
リクオと雪女は見送るしかなかった。
——鴆、飛んで帰れる程…良くなったんだね。良かった――
美しい鳥の姿が見えなくなってから、リクオはおもむろに携帯電話を取り出す。
「…あ、ボクだよ。悪いんだけど、鴆の屋敷まで行って鴆がちゃんと帰ってるか確かめておいてくれる?」
本家の誰かにかけているのだろう。そんなリクオを見て雪女は思う。
——お優しい。リクオ様——
「うん、今、大学なんだけど、鴆の奴、先に帰っちゃったんだ…飛んで…」
用件を一方的に伝えるとリクオは携帯電話をしまう。
「…さ、雪女、他も回ろうか…」
リクオが促せば、雪女は嬉しそうに頷いた。
二人並んで歩き始める。
「…それにしても、あの陰陽師娘が鴆様を…驚きです!」
「…似てるんじゃないかな…」
「ダレがダレにですか?」
「…えっと…鴆が、彼女の兄さんに…」
え?、と雪女は立ち止まる。
「鴆様が、ですか…?」
何処がですか?と雪女は元々丸い目を更に目を丸くした。
「……。…目つきが…悪いトコ…」
リクオはポリポリと鼻の頭をかいた。
3
その美しい鳥は、バサバサッと大きな羽音をたてて舞い降りるや否や、人形へと変化を遂げる。
着流しに羽織姿に戻った鴆は屋敷の戸を潜った。
「鴆様!」
「おぅ、ただいま」
迎え出た蛙の番頭に言葉を返す。
「鴆様、本家から——」
「…済まねぇ。待たせたな」
客間に慌てて姿を現した鴆を待っていたのは本家の首無であった。
「…お邪魔しております、鴆様」
深々と頭を下げる首無に、固い挨拶は抜きだぜ、と鴆は笑った。
「で、今日はどうした?」
問い乍ら腰を据える鴆。
「はい、鴆様のご様子を伺いに」
「オレの?」
笑顔で答える首無に鴆は首を傾げた。
鴆が先に帰ると飛び立った後、リクオが電話をかけていたのは首無であった。
リクオの命を受け鴆の様子を見に来たのだ。
「……。…そいつはご丁寧に…」
鴆は理解した。
頭をポリポリとかいて鴆は苦笑いを浮かべる。心配してもらえるのは嬉しいが、ここまでくると情けなさが溢れてきそうだ。
「…リクオにな、済まねぇと伝えておいてくれや」
「はい。それは勿論」
首無は尚も笑顔であった。
「…とりわけ、お加減が悪い訳ではない様ですね?」
それでは…と、首無は腰を上げかける。
「ちょ…ちょいと待った、首無!」
「はい?」
折角来て貰ったのをただ返すのもどうかと思い、鴆は酒でもと言いかけるが、首無が酒に弱い事を思い出し言葉を飲む。
「何か、鴆様?」
「ちょいと…話していかねぇか…」
鴆は久しぶりに茶を立てた。勿論、酒の呑めない首無の為だ。
「お茶の心得がおありとは…鴆様」
「はは…まぁな」
茶筅を、そっと置き、茶碗を首無へと差し出した。
頂戴いたします、と頭を下げて首無は茶碗を両の手で包む様にして持ち上げた。
「鴆様」
「ん?」
「私は、茶の湯の心得がなくて…その…」
「作法なんか気にすんな。好きに飲め」
鴆は笑う。その笑顔に首無も笑顔で答えて茶碗に口をつけた。
「…昔の事、聞くが…首無」
「はい」
茶碗を置いて、居ずまいを正す首無に鴆は言葉を選び乍ら紡ぐ。
「羽衣狐…京妖怪のコト、覚えてるかい?」
「もちろんですよ、大変でしたからね」
「あん時に…一緒に闘った陰陽師のコトなんだけどよ…」
「はい。花開院家の事ですね」
「そうだ。あの花開院ゆらっていう嬢ちゃんのコト、お前どう思う?」
「…どう、と申されますと?」
ここだけの話だぞ、と鴆は念を押した。
「…つまり…リクオの嫁…として、だ」
「なんと!」
首無は目を丸くした。
「…正気でおっしゃっておいでですか、鴆様?」
首無の言葉に、鴆は返す言葉を失う。
何をどこから話せば、今自分が言わんとしている事が伝わるのだろう。色んな事があったのだ、羽衣狐の一件が終わった時から。
鴆は、くしゃくしゃっと頭をかいた。
「ちと長くなるが聞いてくれるかい、首無よ?」
鴆は話し始めた。六年ほど前のあの日の事から——。
あの日、あの夜、花開院ゆらは突然現れた。
『この度は、三代目襲名おめでとうございます…』
けれど、彼女はそれだけの事で訪ねて来た訳ではなかったのだ。
花開院家の蔵から出て来たという古びた冊子。それには薬の事が事詳しく書かれていた。
自らの毒に苦しむ鴆の役に立つのではないかと、ゆらは鴆にそう言った。
ゆらは鴆の為にその本を持って来たのだ。『役に立つのであれば貰って、役に立たない様であれば返して』そう言って。
その本は役に立つどころの話ではなく、薬師の鴆にとってはとても有り難く嬉しい贈り物であった。
その本のお陰で新しい薬の調合にも成功した。その薬が今の鴆の身体を支えている。
しかし、いくらなんでもこれは貰えないとリクオに返してもらう様言づてをし、本も預けた。
それが数ヶ月前の冬の話。
そして、今日。リクオは鴆にこう言った。
『もしかしたら…彼女は鴆が好きなんじゃないのかな?』
「…そのお話ですと、リクオ様がおっしゃる通り、彼女は鴆様、貴方を好きだという事に——」
「話は最後まで聞きやがれ」
首無の言葉を鴆は遮る。そして、ひとつ大きく息をついた。
「あの嬢ちゃんはな、その本を持って来た時、最後にオレにこう言ったんだよ」
場所を変えて三人で膝を交えた一室での事。
——鳥のお兄ちゃん、アンタにもしもの事があったら奴良くん、きっと悲しむわ。せやからな…元気になって——
しかし、その言葉をリクオ自身は知らない。
誰からか名を呼ばれ、リクオは先にその場を離れたからだ。
それからすぐに鴆とゆらはリクオを追いかけるかの様にその場を離れたが、その時に交わされた言葉。
だからリクオは知らない。
そこまで聞いて、首無はゆっくりと瞬きをした。
「…それでは…彼女は…」
「オレの為じゃねぇ…それだけは確かだ」
鴆は目を伏せた。
「しかし乍ら、鴆様」
水を差す様ですが、と首無は言葉を続ける。
「あれから何年経ったのでございましょう?…恐れながら、人の心は変わりやすいもの…」
あの時は、本当にゆらはリクオに対して好意を持っていたのかも知れない。
共に闘ううちに彼女の中に何かしらの情が生まれたのかも知れない。
けれど、あれから何年経つのか。あれから今も二人の間に何らかの繋がりがあるのであれば話は別だが——。
ならば彼女は『誰の為に』あの『冊子』を携えて来たのだろうか。
やはり、鴆の言う通り、リクオに想いを寄せていると考えるのが妥当という事か。
けれど。
鴆の話ではリクオは花開院ゆらを嫁になどとは考えてもいない様子。
そして、鴆もそんな気など無いどころかこの様な話になって青天の霹靂といった所だ。
どちらも脈は無い。
「夜のリクオ様は…いい男ですからね…」
首無は恭しく小さく笑った。
つづく