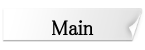縁の糸 6 —— リクオ 嫁取り物語 ——
1
東京駅近くのパーキングに車を止めて、リクオは東京駅へ向かって駆け出した。
余裕を持って家を出るつもりが出遅れ、しかも今日に限って道路が何気に混んでいるのはどういう事なのか。
腕時計の針を確認する。十一時二十五分。到着まで十分を切っていた。
入場券で構内に入り、目的のホームを目指す。ホームへと続くエスカレーターの上で再び時計に眼をやれば十一時三十四分だった。もう、来ている。
ホームへたどり着くと、リクオはあちらこちらへと視線を走らせる。東京駅の新幹線ホームは人で一杯だった。何処だろう。
しまった、せめて服装を聞いておくべきだった、会うのもあまりにも久しぶりだ、見た目もすっかり変わっているかも知れない。これでは——見つけられない。リクオは小さく舌打ちをした。
携帯、そうだ、携帯をならそう——そう思い、リクオは辺りを見回し乍らポケットに手を突っ込んだ。
その時。
トントン。後ろから肩を叩かれた。
え?と振り返れば、そこには着物姿の一人の女性。
「…奴良…くん?」
前下がりボブの黒髪を持ったその人はふわりと笑った。
「まさか着物で来るとは思わなかったからびっくりしたよ」
松林に小舟の柄が可愛い淡い藤色の着物に象牙色の帯を締めた花開院ゆらの姿をリクオは目を細め乍ら見つめた。一目見て値の張るモノと解る着物を難なく着こなすゆらは大したモノだ。家を出る時に身なりに迷ったが、スーツにして良かったとリクオは内心安堵していた。
「こっちの方が陰陽師っぽいと思てな」
奴良くんこそ、スーツ姿やなんて。見違えたわ。背ぇも高こうなって——ゆらはうふふと笑う。
リクオとゆらは東京駅を出たすぐのカフェに居た。大きな吹き抜けがあり、開放感満点である。
「ここ、なんかレトロな雰囲気やねぇ」
ゆらが店内を見渡し乍ら言う。
「うん。この建物は明治時代に銀行だったらしいんだ。ここのランチ、結構美味しいんだよ」
ふうん、そうなんや——ゆらはリクオの説明を聞き乍ら尚も店内を見回していた。
「…今日は…陰陽師としてこっちへ?」
「うん。ほら、電話でも言うたけど…野暮用って言うんは悪霊退治や」
向かい合わせに座る二人のテーブルにランチプレートが運ばれる。二人はフォークを手にし乍ら尚も話を続ける。
「悪霊退治?」
「…って言うたかて、ホンマはどうか解らんのよ?最近は何でもかんでも都合の悪い事は悪霊だの妖怪だのの所為にする人多いし…」
ホンマ参るわ、とゆらは溜め息を付いた。
「そりゃ、大変だ…」
リクオは苦笑する。
現代日本、非科学的な幽霊だのお化けだの、そう言った類いは人々の頭の隅からも追いやられ忘れ去られてゆく一方であるが、ひとたび都合の悪い事が起きればそれは悪霊だのとそれらの所為にされてしまう。とかく人間と言うものは勝手で都合がいい。
「しかも、これ、お兄ちゃんの受けた仕事なんやで。それが私にお鉢が回って来てしもて…」
ま、そのお陰で奴良くんに会えたからえぇけど。とゆらは笑う。
どうやら兄の竜二が来られなくなった為、ゆらが代行で来たらしい。
「聞いて、奴良くん!お兄ちゃんな——」
ゆらはフォークを握りしめて話し始めた——。
「君のお兄さんって…そんなにドジだったっけ?」
ゆらの話によると、ゆらの兄•花開院竜二は乗鞍岳に夏スキーへと出かけ、転び、足の骨を折ったらしい。
「めっちゃ、どんくさいと思わへん!?信じられへん!」
しかし乍ら、悪霊退治依頼を断る訳にはゆかず、今こうやってゆらが東京まで出来た次第という訳だ。
「こんなんでキャンセルしたら花開院家の恥やろ?」
そう言って最後の一口をパクリ。ゆらはランチプレートを綺麗に平らげた。
「うん、美味しかった」
満足満足と微笑むゆらに、だろ?とリクオは笑った。
「で、その悪霊退治ってのは?」
「…うん…北区赤羽の…えっと…」
そう言い乍ら鞄をゴゾゴソとかき回すゆら。
赤羽——殆ど埼玉じゃないか。リクオはゆらかメモを受け取り、そこに書かれた住所に眼を走らせた。
「約束の時間は?」
「三時頃には行きますって言ってあるんやけど…」
「そう。…じゃ、今から出ようか。ここから車で行けば充分三時には間に合うよ。早く着くには問題ないだろ?」
とリクオはメモをゆらに返すと、テーブルの上に置かれた伝票に手を伸ばした。
「え…付き合ってくれるん?」
「ここで、ハイさようならって訳にはいかないだろ?」
リクオはゆらを連れてカフェを後にした。
2
二人は蔦の絡まる古びた洋館の前に居た。
「…ここか…?」
「うん、多分。ほら、表札の名前…間違いないわ」
ホンマ、なんか出そうなカンジやわ、そう言い乍らゆらはチャイムを押した。
ようこそいらっしゃいました、と型通りの挨拶を受けて、リクオとゆらはこの家の女主人と思われる老女に家の中へと通された。
「まずは客間へご案内いたします…お茶でも」
え、あ…はい、と小さく返事をするゆらを制してリクオが一歩前へ歩み出た。
「いえ、早速ですが、その悪霊が出るという部屋に案内して下さい」
「…えっと、奴良くん…」
リクオの腕を慌てて引っ張るゆら。
「はぁ。…失礼ですが、あなた様は?」
老女は首を傾げた。
「ボクですか?…ボクは…花開院ゆら先生の助手です」
ちょっと、ちょっと助手って奴良くん!——慌てるゆらを、いいからいいから、とリクオは完璧な笑顔で黙らせた。
そこは地下にある十二畳程の和室であった。その部屋には床の間があり、そこに件のモノが鎮座していた。それは鎧。
「これが夜な夜な音を立てて騒ぐのです…夜の方が宜しいのであれば、陽が落ちるまでおくつろぎ頂いても…」
「…解りました。後はこちらでやります…お任せ下さい」
夜まで待つには及びませんよ、とリクオは老女に笑顔を向けると退出を促した。
そして部屋にはリクオとゆらの二人きりとなった。二人は床の間に鎮座する鎧に向き直る。
「確かに何か憑いていそうだね…。さて…」
始めようか、とリクオは小さくニヤリと笑った。
「…ありがとう、奴良くん。お陰であっさり片付いたわ」
「…どういたしまして」
二人は件の洋館を後にして、車で元来た道を走っていた。
「けど、びっくりした。いきなり祢々切丸出すんやもん。あれって夜の姿でしか無理と違うん?」
「無理じゃないから出してみせたんだけど?」
リクオはハンドルを握り乍ら笑った。
「場所が地下で良かったよ。お陰で闇には困らずに済んだ」
いつの頃からか古い鎧に憑いたそれは、何も悪さをしようなどと企んでいる訳では無く、ただ、己の行き場に困り夜な夜な嘆いていただけであった。
『こんな所で夜な夜な騒いでいちゃ、いずれ滅せられるぜ?どうだい、オレのシマに来ねぇか?悪い様にはしねぇ。…浮世絵町の奴良組を訪ねて来な。テメーには違う器を誂えてやる』
そう言ってリクオは、昼の姿のままに祢々切丸を肩に担いでニヤリと笑って、それを鎧から引き剥がしてしまったのだった。
「けど、ええのん?あれ、奴良くんとこに来るかも知れへんよ?」
「いいよ、来たら来たで。君たち陰陽師の努めが妖達を滅する事なら、ボクの努めはそれらを総べる事だからね…」
「…。…奴良くんはホンマ、魑魅魍魎の主やねんなぁ…」
「で、これからどうする?日暮れまでにはまだ時間はあるし、何処か行きたい所は?」
行きたい所、と問われてゆらは首を捻って思案した。実のところ東京はあまりよく解らず返事に困った。
「…東京タワー…」
思案したあげく、ポツリとゆらは答えた。
「うわぁ、遠くまで見えるんやね!」
ゆらは東京タワー特別展望台で感嘆の声を上げた。
「ほら、あそこに富士山が見えるよ」
リクオが指差す方向を見やれば、白い山の頭が見えた。
「へぇ富士山見えるんやぁ…」
「今日は天気がいいからね」
「うん」
藤色の着物の美しい女(ひと)は展望台からの景色に心を奪われているようであった。
リクオはそんな彼女を横目に見ては、本当に綺麗な女(ひと)だと思った。
女は化けるというけれど、こういうことをいうのかと改めて感じていた。展望台に居合わせた他の客達も時折ゆらに視線を送っている。それ程に、ゆらは綺麗だった。
他の客達からは自分たちは一体どう見えているのだろう?さぞかし『あんな綺麗な娘(こ)にあんな冴えない男』と思われているに違いない。そこまで考えてリクオはと小さく零した——なにを馬鹿な、と。
「…え?なんか言うた?」
「いいや、なんにも。陽が落ちる前に、ここから見える景色を説明しておこうか——」
いいかい?とリクオはゆらの真後ろに立った。リクオより頭一つ分背の低いゆらは、リクオの顎の下にすっぽりとおさまり、リクオはゆらの頭の上に顎を乗せる様な格好で指を指し示しては説明を始めた。
3
「いらっしゃいませ!」
通された奥の個室。スッと空いた襖の向こうにゆらは目を丸くした。
「あなたは!?あの旧鼠の時の!?」
「へい、良太猫でごぜいやす。その節はお世話になりやした」
ペコリと頭を下げる良太猫。ちょっと見ない間に綺麗におなりで、と愛でる言葉も忘れない。
「ここは良太猫の店なんだよ。料理も旨いし、なかなかいい店だよ」
東京タワーの展望台から見える景色を楽しんだ二人は、少し早いが夕食にしようと再び車を走らせた。
居酒屋とかって…行った事ないねん。いっぺん行ってみたい——ゆらのその一言でリクオはゆらを此処•浮世絵町一番街にある良太猫の経営する化猫屋へと連れて来たのだった。
既にテーブルには数々の料理が並べられている。
ごゆっくり、とひとつ頭を下げて部屋を辞した良太猫を見送って、さ、遠慮なくどうぞ、とリクオが料理を進めれば。
「ほな、まずは乾杯、な?」
「うん」
お疲れさま、と二人はウーロン茶の入ったグラスをカチンと合わせた。
「ホンマに今日はありがとうな、奴良くん。大助かりやったわ」
「どういたしまして。お易い御用だよ。なんならこれからも助手してあげようか?」
ほんの少しニヤリと笑ってみせる。
「なっ!?なに言うてんのん!あかんあかん!お兄ちゃんにバレたらシバかれるわ」
ゆらはグラスを置いて、両手を顔の前で振る。
「大丈夫だよ、君の兄さんは君には甘いから」
「そんなことあらへんわ」
「いやいや、泥甘だって」
気付いてないの?とリクオは笑う。
「足、崩した方がいいよ…楽にして」
ボクも楽にするから、とリクオは上着を脱いでネクタイを緩めると胡座をかいた。
「…奴良くん…仕事帰りのくたびれたサラリーマンみたいやで?」
プッと吹き出してゆらは口元を押さえた。
「くたびれた、は酷いな」
リクオはそれは余りにも心外だと顔一杯に不満の言葉をのせた。
「なんか奴良くんの将来がちょっと見えた気ぃしたわ」
ゆらは目を細めて、正座の足を崩し横座りする。
夜はともかく、昼のこの青年は何処から見ても真面目な好青年だ。会社勤めをしたとしたらきっとこんな風なのだろう。
「なんやしらん、このお店…賑やかやなぁ…」
二人の通されたのは襖で仕切られた個室だが、それでも襖の向こうの笑い声やグラスを交わす音、店員が注文を取る声が絶え間なしに聞こえてくる。
「はやっているからね、この店は」
「ココも奴良くんトコのシマなんやろ?」
「そうだよ」
「ほな、実質奴良くんがココのオーナーちゅうわけやね?」
「うーん…オーナーってのはちょっとニュアンス違うかも…ね」
オーナーなどと言われると、なんだか青年実業家の様だ。リクオは苦笑する。
「奴良くん大学通ってるんやったっけ?彼女とか居てるん?」
「居ないよ」
「そうなんや」
「だから…さ、バレンタインもチョコくれるのはウチの組の雪女くらいだよ」
そう言い乍らリクオは焼鳥の串を口に運んだ。その姿が本当にくたびれたサラリーマンに見えて、ゆらは笑いそうになってしまう。
「律儀やなぁ…及川さん」
「そうだね、自慢の下僕だよ」
下僕——その言葉にゆらは、あぁ、この人はやはり人ではないのだなぁと感じた。
関東任侠妖怪総元締奴良組三代目総大将•奴良リクオ。目の前に座る優しい面差しの青年の正体だ。
「なぁ、奴良くん?」
「ん?」
「……。…家長さんとは仲良ぅしてんの?」
「え?なんで?」
「…なんでって…あんたら両思いやろ?」
「えぇ?!」
両思いといわれてリクオは手にしていたグラスを落としそうになった。
「え?違うのん?」
「…ち…違うよ…。カナちゃんとは只の幼馴染みだよ」
どうしてそうなるかなぁ、とリクオは顔を引きつらせた。
「それに、カナちゃんは今では時の人だからね」
「時の人?」
「知らないの?モデルになったんだよ、彼女。最近は歌も出したみたいだし…。だからもう、この町には居ない」
「…そうなんや…。で、それでえぇのん?」
「いや、だからそんなんじゃないから…」
ふうん——ゆらは少し考えて、また口を開いた。
「昔な、私、家長さんに聞いた事があるねん——」
『家長さん、奴良くんの事、おしえて』
『いいけど…リクオくん、わたしの事好きだと思うよ』
「そんなん言うてたから、わたしはてっきり今は恋人同士か何かかなぁって思てた」
そんなゆらの言葉をリクオは黙って聞いていたが、一つ息を付いて口を開いた。話しておこうか、と。
笑顔の消えたリクオの瞳にゆらは一瞬身を固くした。人の姿のリクオのそれに夜のリクオを垣間見た様な気がしたからだ。
「カナちゃんは——カナちゃんはね」
グラスのウーロン茶を一口飲んでリクオは話し始める。
君も知っての通り、ボクには1/4妖怪の血が流れている。
だから夜になるとその姿も変わる。彼女にはずっと隠していた事だけれど…それも限界がきた。つまりバレたんだ。
君は夜と昼、両方のボクを認めてくれたけれど彼女は——。
「一生懸命理解しようとしてくれたんだと思う。けど、頭で理解は出来ても心がそれを拒絶したんだ」
そんな矢先、本格的にモデルデビューの話が舞い込んだのは彼女にとっては渡りに船だった事だろう。
「…なんか無理してるなって見てて解ったし。そんなカナちゃん見るのも辛かったし。だから——」
苦笑いをひとつ零した。
「それ、家長さんにちゃんと確かめたん?」
「…え…あ…いや…。それは…してないけど…」
「ほな、家長さんのホンマの気持ちは誰も解らへんってコトやんな?」
テーブルに並べられた料理をパクパクと口に運び乍らゆらは言った。お似合いやのに、そら残念やなぁ、と。
「今日は、東京に泊まって明日の朝の新幹線で帰るんだったよね?」
「あ…うん…」
「…そろそろ、出ようか」
リクオは立ち上がり、良太猫を呼びつける。
「総大将、お帰りで?」
「うん、お勘定頼むよ」
「いえいえ、若からは頂けやせんや!」
良太猫は目の前で両の手を広げて大きく振って見せた。
「そうはいかないよ。いくら?」
「ちょっ…ちょっと待って、奴良くん!今度は私が…私に出させて」
お昼も奢ってもらったし、とゆらは財布を取り出したが、男に恥かかせないでよ、とリクオは笑ってゆらを制した。
化猫屋の精算を済ませたリクオはゆらを連れて店を後にする。そんなリクオを良太猫は深く頭を下げて送り出した。
「総大将の…恋人ですかね?」
美人でしたね、と笑う三郎猫に良太猫はそうだなと小さく答え乍ら——。
——闇が支配する刻限となっても昼のお姿のままとは…総大将——
良太猫と三郎猫は二人の背中が小さくなるまで見送った——。
つづく