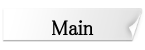縁の糸 7 —— リクオ 嫁取り物語 ——
1
客間に通されたゆらは借りて来た猫の様になってしまっていた。今日は、東京駅付近のホテルで一泊し、明日朝一番の新幹線で京都へ帰るつもりをしていたのだが、何を間違ったのか、ゆらは今、奴良組本家に居た。
『…ウチに泊まるといいよ』
化猫屋を出て車に乗り込んだリクオの第一声がこれだった。冗談ではない、と断りを入れようとしたゆらにリクオは更に追い討ちをかけたのだった。
『爺ちゃんに会いたくない?鴆には会いたくない?』
そう言われて、心が僅かに揺らいだ。そしてそんな心を見透かされて、今此処に居る。
以前泊まった時は、リクオの母•若菜の部屋で過ごしたが、今回は客間を一部屋与えられた。
しかし、いつまでもこうしていても仕方が無い。ゆらは腰を上げた。
「お湯、頂いてこよう…」
まるで旅館の様な大浴場で一日の疲れを流し、濡れた髪をタオルで拭き乍ら部屋へと戻ろうとした時、ふいに後ろから声を掛けられた。
「…風呂上がりも、なかなかいいじゃねぇか…」
その声に慌てて振り返れば赤い瞳のリクオが立っていた。それはゆらが苦手とする夜のリクオであった。ゆらはゴクリと生唾を呑む。
「…鴆が来てるぜ…」
「鳥のお兄ちゃん!奴良くんから聞いてたけど、ホンマ元気になったんやな!」
良かった、本、役に立ったんやな、とゆらは顔を輝かせ、鴆に抱きついた。
「おいおい…お嬢ちゃん…」
飛びつくゆらを抱きとめて鴆は微笑んだ。そして小さくこう言った。えれぇ別嬪になっちゃじゃねぇか、と。
「ホンマ?私、綺麗?」
「本当じゃ、まこと美しくなったのぅ…」
眼を細めるぬらりひょんに、ゆらはいややわぁ、と微笑んだ。まんざらでもないらしい。
「おじいちゃんも鳥のお兄ちゃんも元気でなりよりや」
微笑むゆらは本当に嬉しそうであった。そんなゆらを距離をおいて横目にちらりと見やるリクオは無表情のままに杯を傾けていた。
ゆらは奴良組本家の妖怪達とは総じて仲がいい。京都で共に闘った所為もあるだろうが、何より妖怪達に対して理解があった。
ゆらは元々、妖怪は悪であり滅するもの、と信じて疑わなかった。けれど、それは違うのだと気づき、その考えを改めた。それからというものは妖怪というものに対しての理解は深くなっていった。その切欠を作ったのは他でもないリクオであったが、しかしリクオにはその自覚は無い。
まるで自ら壁を作るかの様に距離をおき、独り酒を煽るリクオの傍に雪女が腰を下ろした。
「リクオ様」
酒の入った蒔絵銚子を手に取って、リクオを伺う。リクオは杯の酒を飲み干すと雪女についっと差し出した。雪女はニッコリと微笑むと酒を注いだ。
「なんで、あんな女がここに居るんです、リクオ様?」
少々頬を膨らませて雪女は小さな声でポツリと言った。
「…。…ま、成り行きで…」
ボソッと答えるリクオ。
「滅せられますよ!封印されちゃいますよ!」
「心配するな、雪女。そん時ぁ…オレがお前を守ってやる」
コトリと杯を膳に置き、リクオは雪女の抱き寄せた。
「…!…リクオ…様…」
雪女は僅かに頬を染めて、膳に置かれた杯をリクオに差し出す。
「どうぞ…リクオ様」
「…あぁ…」
雪女の手から黙って杯を受け取れば、雪女が蒔絵銚子を傾けた。
鴆はゆらと以前彼女が持参した薬の本の事で話に花を咲かせていた。話に花を咲かせ乍らも、雪女の酌で酒を煽るリクオに時折視線を投げていた。
そんなリクオと鴆をなにやら思案気に傍観する初代総大将•ぬらりひょん。
雪女のヤツ、リクオから離れやがれ。リクオもリクオだ、何してやがる、バカモンが——鴆は小さく舌打ちをした。
2
「こんな所で何してやがる?」
にしても、よく登ったな、とリクオはニヤリと笑ってみせた。
「うん…ここに居てたら…奴良くん来るんやないかなぁ…って思てな…」
ゆらはリクオには眼を向けず、空を仰いだ。天上には青白い月が煌煌と輝いている。
ここは奴良組本家の庭、枝垂れ桜の枝の上。いつもならばリクオが座っている場所にゆらが陣取っている。そしてその傍に銀の髪をなびかせたリクオが立っていた。
「ちょいとどきな」
リクオはゆらの背をトンと押した。え?と桜の幹からゆらが背を放せば、リクオはそこへと滑り込んだ。
「え…え、えぇ?」
慌てるゆらを尻目にリクオはゆらの背中を抱き込む様な形で座り込んだ。
「ちょ…ちょ…ちょっとっ!」
「暴れんじゃねぇ…落ちても、知らねぇぜ?」
リクオの右手がゆらの腹に回される。それにピクリとゆらは身体を震わせたが、それはほんの一瞬で僅かであった。
けれど――きっとそれは気付かれたに違いない。ゆらは思った。
「…雪女と…仲良さそうやね。そっか雪女が居てるから家長さんの事は吹っ切れたんやね」
リクオは何も答えずゆらの言葉を只聞いている。
「…さっき見てて思た…なんかお似合いやったよ。もしかして、雪女って奴良くんのお嫁さん候補なん?」
首を捻ってゆらはリクオを見た。
「…そう、見えるのかい?」
そりゃ、とんだ姉さん女房だな、とリクオは無表情のまま小さく答えた。
「え?雪女って奴良くんより年上なん?」
「年上も年上。オレが小せぇ時からの世話係だからな」
「それって…乳母さんみたいなもん?」
「乳母って…お前…」
雪女が聞いたら怒るぞ、リクオは鼻の頭を左手の人差し指でかいた。
「それより、お前の方こそ、どうなんだい?」
「どうって?」
「久しぶりに鴆に会って、鴆と話して…どうだったって聞いてんだよ」
「あ…あぁ…それはもう、嬉しかったよ。お爺ちゃんにも会えたしな」
ゆらは笑顔を見せる。
「…それだけ…かい?」
リクオは眼を細めた。
「…奴良組本家はホンマ賑やかでえぇね。ウチも人数は負けてへんけど、ここみたいな賑やかさはあらへん…」
ゆらは視線を外して前に向き直った。
「答えになってねぇな」
リクオは右手に力を込めて引き寄せた。ゆらの小さな背中はトンとリクオの胸に当たる。
「…あんな薬の本を持って来るなんざ回りくどい真似しなくても、オレに言やぁきっちり鴆との間、取り持ってやるってもんだぜ?」
それともジジィがいいのかい?とリクオはゆらの耳元で囁いた。
「私は…お婿さん貰ろて、家守らなあかんもん…」
穏やかに言うとゆらは肩越しにリクオを見た。
それは花開院家とぬらりひょんにかけられた羽衣狐の呪い。
その呪いにより花開院本家の男子は早世してしまう。故に代々分家より養子を取り血を絶やす事無く今日まで至っている。
羽衣狐は倒したが、だからといってその呪いが解けたという保証は何処にも無い。呪いが解けていればいいが、そうでなければゆらの兄•竜二は永くないという事になる。血を守る為には自分が容姿を迎える他は無い。
「…代々、ウチの家はそうやってきたから、いつか自分もって思ててんけど、いざ自分の番がきた思たら…なんやしんどなってきた…」
ゆらは寂しそうに笑う。
「…なぁ、奴良くんは…三代目継ぐのん、迷った事無かったん?」
「…迷ってたぜ…『昼のオレ』はな…」
赤い瞳に影を落としてリクオは答えた。そんなリクオを見てゆらは眼を見開く。
「……。…そう…やんな…。…そんなん決まってるやんな…」
ゴメン、奴良くん。ゆらは視線を外した。
「けど、奴良くんは偉いなぁ。だってな、それ、十二歳の時に答え出したんやろ?…私は…十八になってもまだどっか迷てる…」
いつの間にかゆらは背中をリクオに預けていた。
「いいんじゃね?…年は関係ねぇよ…」
リクオは空を仰いで呟く様に答えた。
3
「狐の呪い…解けたんやろか…?」
「…さぁ…な…。…お前の兄が早世せず子を成し、そしてオレが妖怪と交わり子を成せれば…呪いは解けたって事だ…」
「…子供が生まれへん呪いって…。そんなにあの狐は私らが憎かったんやろか?」
「そうじゃね?」
自分が悪いくせにな!再びゆらは身体を捻ってリクオに向き直ると眉根に皺を寄せて言い捨てた。
「…そんな顔してっと皺になるぜ?」
リクオの左手の親指の腹がゆらの眉間の皺を押さえた。
「呪い、解けてて欲しいな…。あんなお兄ちゃんやけど、大事なお兄ちゃんやから…」
「…ドジで性格悪いけどな…」
「うん、そやねんけど…って酷い、奴良くん!」
振り上げられたゆらの右手をリクオの左手が掴む。
「ははは…お前だって今認めたじゃねぇか」
リクオは笑った。
「…あ…」
ゆらは初めて見た様な気がした、夜のリクオの笑顔を。そして慌てて振り上げた右手を引っ込めた。互いの手が離れる。
「…え…?…」
ほんの一瞬沈黙が流れた。
「な…なぁ、奴良くん!」
「なんだよ?」
「奴良くんのお婆ちゃんもお母さんも人間なんやろ?それは…呪いの所為でそうするしか無かったからなん?」
「…いや…ジジィは違う。ジジィは呪いを掛けられる前から婆ちゃんに決めてたみたいだからな。…親父は…親父も違うと思う。たまたま惚れたのが人間のお袋だったってだけだ…」
「そうやんなぁ。奴良くんのお父さんとお母さんって大恋愛やってんもんな!」
ゆらは六年前の若菜と交わした会話を思い出し乍ら笑った。
『妖怪でも人間でも私はあの人と結婚してたわ』
「奴良くんもそんな大恋愛出来たらえぇなぁ!応援してるわ!」
「……。結構だ」
ポンと肩を叩くゆらの手をリクオはやんわりと払った。
「え?何照れてんのん?」
「照れてなんかいねぇ!」
「うそぅ!照れてるやん!」
「うるせぇ!」
池に落とすぞコラ、と眉間に皺を寄せるリクオ。
「落とせるもんやったら落としてみぃ?そんなんしたら今度こそ滅したるからな!」
「おぅ、上等だ…やってみやがれ、ヘボ陰陽師」
ニヤリとリクオは笑う。
「誰がヘボやねん!破軍出すで!」
「おうおう、出しやがれ。ジジィが喜ぶ」
今ではゆらの式神となった十三代目秀元。その昔、祖父•ぬらりひょんと共に羽衣狐を倒した間柄である。
「なぁ、そうだよな、ジジィ?」
リクオはチラリ真下に視線を投げた。
「…いつまで盗み見してやがる!」
「え?お爺ちゃん?えぇ?!」
ゆらはリクオの視線を追うが、そこには何も無い。否、無かった。が、しかし。
「バレとったとあっては仕方無いのぅ…」
ふぉっふぉっふぉ、と笑い声が聞こえたかと思えば、そこにその姿がはっきりと浮かび上がって来た。少なくともゆらの眼にはそう見えた。
「なかなか良いむ〜どじゃのぅ。どうじゃ、ゆらちゃん、リクオの嫁にならんか?」
「余計な事言ってんじゃねぇ!」
「ゆらちゃん、またな」
リクオが怒鳴れば、ぬらりひょんは豪快に笑って屋敷へと戻って行った。
「…いつから…お爺ちゃん居てはったんやろか…?」
恐る恐る問うゆらに、リクオは飄々として答えた。流石ぬらりひょんの孫である。
「オレがここに来てすぐじゃね?ずっとあそこに居たみてぇだ」
「居たみたいって…なんで教えてくれへんの?!」
という事は、今までの会話を全部聞かれてしまった事になりはしないか。聞かれてまずい話しはしていないが、それでもゆらは何か恥ずかしさで一杯になった。
「だからお前はヘボ陰陽師だってんだ…」
しょうがねぇな、とリクオは眼を細めて笑った。
つづく