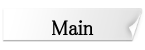小雪春 5 —— 鯉伴 嫁取り物語 ——
1
鯉伴はその日、自室に籠っていた。
座卓の上に頬杖を付き、古い書物を広げて目を落としている。しかし、その目は文字を追う事は無く、その項も捲られる事は無かった。
外は雨、しとしとと雨音が閉ざした障子の向こうから聞こえてくる。閉ざされた空間には沈香の香り。
いい香り、と言ってくれた。——若菜。
あれから奴良組本家には不穏な空気が漂っている。
——聞く所によれば、総大将に女が出来たとか。
——それも人間だというではないか。
——よりによって、また人間とは。
——ますます妖の血が薄まってゆく。
——今度は大丈夫なのか?
——これから奴良組はどうなるのだ?
お前が誰を好きになろうとお前の自由。お前個人の勝手。なれどお前は総大将。その一挙手一投足に古参妖怪どもが騒ぐのも致し方の無い事。
そう言ったのは牛鬼。
そんなこと、百も承知。言われなくても解っている。何百年、この奴良組の総大将をやっていると思っているのだ。
総大将として、世継ぎを残すのもまた努めなのだろう。それも重々承知。
けれど、この身は呪われてしまっている。生まれたときから。
妖との間に子は——成せぬ。
子を成そうとすれば人間と交わるしか術はない。
世継ぎ欲しさに人間の女を傍に置くか。その為だけに。そして、そこに通い合う心がないとしたら。
そんな両親を持って生まれた子は幸せか。
人と妖の間に生まれて、人でもない妖でもない、半端な存在。そんな半端な存在に生まれて尚、自分が幸せだと思えたのは両親が仲睦まじかったからだ。
仲の良い両親の姿に、幾度となく顔を綻ばせた。
折角生まれて来るのだ。そう思って貰いたいじゃないか。自分がそうだった様に。
そう願ってやまない自分が居る。人としての自分自身が。
——大体なぁ、相思相愛の相手がそう簡単に見つかってたまるかってんだ。見つからねぇから苦労してんじゃねぇか——
確かに両親は相思相愛ではあったが、それはあくまで結果論である。その馴初めときたら、当然乍ら聞いた話ではあるが、まんま拉致だ。
頭の先から足の先まで、まんま妖の父は欲する事に躊躇しない。欲しいモノは欲しいと言う。
そんな父に母も最初は困惑したに違いない。
それが、どこでどうなってあの母があの父の何処に惚れる事となったのか、それはいまだに鯉伴にとっては大きな謎なのだが、母がまだ健在の頃、仲睦まじい両親のその姿に嘘はないと強く感じたモノだ。
そんな妖である父の様な強引さがあれば…とも思う事もあるが、とてもじゃないがあんな強引グマイウェイな行動の真似事は一生出来そうもない。
もし、あんな…父が母にした様な仕業を自分がしたら——したら。
どう思われるだろうか。
どう思われる——誰に?
誰…に。
そこまで考えた時、廊下に面した障子の向こうから声がした。父の声。ふと我に返って応える。
「なんじゃ、出かけておったのではないのか?」
「この雨じゃ、出かける気も失せるってもんだ」
鯉伴は、溜め息まじりに座卓の上の書物を閉じては脇へと放って、入ってきた父•ぬらりひょんに答える。
「…長雨の季節じゃからのぅ…仕方無いわい。じゃが、もう文月、もうじき梅雨も開けるじゃろうて」
ぬらりひょんは開け放たれた障子の向こう、庭の枝垂桜に目をやりながら独り言の様に呟いた。
え——?
鯉伴は父の言葉にふと部屋の隅に掛けてある暦へと視線を移した。掛かる暦は——水無月。
「…親父…」
「なんじゃ?」
「…今日は…何日だい?」
おかしな事を聞くな、とぬらりひょんは笑う。
「いいから、何日だい?」
「なんじゃ、おまえ、文月も半月を過ぎようかというのに暦を捲っておらなんだのか?」
「…七月…十五日…」
慌てて暦を捲る——なんて事だ。鯉伴は前髪をくしゃりとかきあげた。ふと時計の針に視線を投げる。丁度昼を回ったばかりという頃。
「出かけてくる」
「なんじゃ、さっき出かける気も失せると言ったばかりではないか?」
ぬらりひょんの呑気な声に、あぁ?そうだっけ?と適当な応えをして鯉伴はそのまま廊下から庭に出ると、とん、と地面を蹴って——そして消えた。
ぬらりひょんは倅が消えたその場所を眺めながら溜め息をひとつ。やれやれ——と。
——なぁ、鯉伴よ。儂はな、人の娘が悪いと言っている訳ではない。
その様な物言いをすれば、儂自身を否定する事となってしまうからの。儂もまた人の娘を娶った。
——解っている。
——じゃが、お前は総大将じゃ。
組を統べるのが努め。
——解っている。
——お前には『前』がある。今度また何かあっては…。
山吹乙女には可哀想な事をした。
——解っている!
「…ちと言い過ぎたかの…」
ぬらりひょんは独りごちた。
「…総大将はお出かけでございますか…?」
「おお、鴉天狗か。…どうやらその様じゃのぅ」
「あの、娘の所でございましょうか?」
「かも、知れんのぅ」
「よろしいので?」
「良いも悪いも、無かろうよ」
「しかし、先日の総会の時もそうでしたが…不穏分子が増えつつありますぞ」
鴉天狗の言葉に、ぬらりひょんは答えなかった。
沈香の仄かな香りがゆるり流れてきては鼻孔をくすぐる。
よい、香りですな、と鴉天狗。
「最近あいつはこの香をよく焚いておるの…」
2
「テスト休みくらい、ゆっくりすればいいのに」
ま、うちは助かるけどね、と洗ったばかりのグラスをフキンで拭き乍らマスターは笑った。
「家に居ても独りだもん。…だから…私、お休みの日は大嫌い…」
冷めた紅茶を口に運んで、制服姿の若菜はポツリと呟く様に言った。
此処は若菜がアルバイトをする『銅鑼夢舘』という名の喫茶店。この日は昨夜から続いている雨の所為か店内には客は無く、マスターと若菜の二人きりだった。
いつものごとく、カウンター席の隅っこに腰を落ち着けた若菜は、カウンターの中のマスターと語り合っている。
「でも、独りもだいぶ慣れてきちゃった。それはそれでちょっと悲しいけど、でもそうならなくっちゃいけないし…ね」
若菜はふわりと笑う。
二年前の冬、突然一度に両親を失ってしまった。寂しくて悲しくて、涙が止まらなかった。
けれど。
いつまでも泣いているわけにはいかない。泣いても死んだ者は返って来ないのだから。
「はやくいい人見つけなくっちゃね」
マスターの言葉に、ほんの少し頬を赤らめて、うん、と頷く若菜。そんな若菜をマスターは目を細めて見つめる。
可愛い娘だと思う。将来この娘の隣に立つ男はどんな男なのだろう。
このままこの店を手伝ってはくれないだろうか、高校を卒業してもずっと——時期が来たら一度言ってみよう、とマスターは思う。
若菜はまだ高校生、それを言うには今はまだ少し早すぎる。
でも——と、そんな若菜にマスターは動かしていた手を止めた。
「人恋しさと愛しさを履き違えてはいけないよ?」
え——?若菜はふと顔を上げてマスターを見返した。
人は寂しくなると、人恋しくなる。けれど、その『人恋しさ』は『愛している』とは違う、別物だ、とマスターは語る。
「君の寂しい気持ちにつけ込む男が居るとも限らない、そういう事だよ」
僕もその一人かも知れないね——マスターは心の中で呟いた。
「………」
若菜は黙ってマスターの言葉を聞いている。
「…もし、今、君の中に気になる人が居るのなら…よく考えてごらん。本当に好きなのか、どうか…ね」
「…本当に…好きかどうか…」
自分に言い聞かせるかの様に、若菜は小さく繰り返した。
「あ、さては居るんだ?」
茶化す様に問うマスターに若菜は真っ赤になって顔の前で大きく手を振る。
「ちっ違いますっ!そんな…私…」
そんな人…まだ居ません、と小さく否定した。
そうかそうか、とマスターは笑う。
あら?——若菜は辺りを視線だけを動かして見渡した。
「ね、マスター…お店、アロマでも使ってるの?」
「アロマ?…そんなもの…。この店のアロマっていったら、珈琲の香りと今君が飲んでいる紅茶の香り、そんなトコだよ。どうして?」
「うん…なんだかいい香りがした様な気がしたから…」
そう言い乍ら、若菜は店の中を見渡し乍らクンクンと匂いを嗅いでいる。——この香り、なんだったかしら?
「あぁ、そうだ。良かったらこれ…友達とでも行くといいよ」
マスターはシャツの胸ポケットからそれを取り出してカウンターの上に置いた。
これは?——若菜はそれを手に取った。
「あぁ、これ。夢咲き公園のチケットじゃないですか?どうしたんです?」
夢咲き公園とは、此処から電車で駅三つ程行った所にある小さな遊園地で、規模こそ小さいがその歴史は古く、若菜も幼い頃から何度も遊びに行った記憶のあるところであった。
夏恒例のお化け屋敷のポスターを貼らせてくれとこのチケットを置いていったのだとマスターは説明した。
「…そっか…お化け屋敷…か」
もうそんな季節なのだな…と若菜は小さく笑う。
「うちはほら、こんな店だし、貼っても客寄せにはならないよって言ったんだけどね…」
「で、そのポスターって…?」
「ほら、その後ろ…」
マスターは若菜の背後を指差した。それにつられる様に首を捻って視線を移す若菜。
そこにはいかにもなお化けが描かれたポスターが貼られてあった。
「!?」
それを見て若菜はピクリと肩を震わせた。
あ、珈琲が無いな…すぐに戻るよ、とマスターは呟いて店の奥へ入って行ってしまったが、若菜にはマスターの声が届いていなかった。
若菜が肩を震わせたのは、それはポスターではなく——。
「…よぅ…若菜ぁ…」
お化け屋敷のポスターの貼られた壁の真下。そのテーブルに煙管を銜えてニヤリと笑う黒髪の男の姿があった。
「…鯉伴…さん…。…いつからそこに…?」
今この店には客は無く、マスターと自分の二人きりの筈だった。
良い香りが若菜の鼻孔をくすぐった。——この香りは…あぁ、これは沈香。…さっきから気になっていたのはこの香り。微かに香っていたので気が付かなかった。けれど、今は強く強くその香を感じる。
「…さっきからずっと…」
「そんな事ないわ。さっきまで誰も居なかったもの」
「居たんだよ…ずっと」
でも——と言いかけた若菜を鯉伴は制した。奥からマスターが戻ってきたのだ。
「…どうした、若菜ちゃん?」
「え?」
戻ってきたマスターに若菜は向き直った。
「…ポスター…怖かった、とか?」
クスクスと笑ってマスターは壁に貼ったお化け屋敷のポスターを指差した。
若菜はもう一度それが貼られた壁へと視線を投げる——そこにはもう誰も居なかった。
——消えた?…さっきまで居たのに…どういうこと…?——
「…結構、おどろおどろしいよね。あのポスター」
「…え…あぁ…そうですね。…でも、実際はそうでもないのかも…」
ちらりとマスターに視線を返して、若菜はまたさっきまで鯉伴が居た筈のテーブルを眺めた。
若菜の言葉に、そうかもね、とマスターは笑った。
つづく