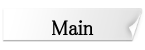小雪春 6 —— 鯉伴 嫁取り物語 ——
1
「びっくりしたわ。いきなり居るんだもの」
ずっと聞いてたの?若菜は形の良い唇を尖らせた。
「…まぁ…な…」
港。
若菜と鯉伴は二人して海を見ていた。
日中降り続いていた雨は日暮れ前には上がり、今は雲間も途切れて下弦の月がと幾つかの星々が夜空にアクセントを添えている。
陽もすっかり落ちて、辺りは闇が支配する時刻となった。天の明かりが失せれば、かわりに地の明かりがそれの代わりに辺りを照らす。
いつの頃からか、この日本には『闇』が消えていった。
それに伴い我ら妖も消えてゆく定めなのだろうか——それが定めなのであれば、それに倣うまで、と鯉伴は思う。
けれど。
消えゆく定めであろうとも、それでも組は守らねばならない。それが総大将たる自分の努めだ。
総大将。いつもこの名が付きまとう。今に始まった事ではないが、何だろう——この倦怠感。
「…さん…?…鯉伴さん?」
声に気付けば、若菜が小首をかしげてこちらを見ていた。
「…あ…あぁ…済まねぇ…ちと、考え事を…」
そう、と若菜はふわりと笑った。
「久しぶりですね」
「…先月の月命日は済まない事をした。すっかり失念しちまっていた…」
「忙しかったのですね」
「…お袋の墓も…済まなかった」
「あら、なんのことです?」
「恍けるんじゃねぇよ…綺麗になってた」
「お墓参り、行ったの?」
「…ん…まぁ…」
「よかった。お母さんも喜ばれてますよ?」
「あぁ、若菜が綺麗にしてくれて…喜んでるさ」
「そうじゃないわ」
「あん?」
「あなたがお墓参りしてくれた事に喜ばれてるのよ?」
解ってないのね、と若菜は笑った。
「あぁ…そうだ、あの店、なんて読むんだい?」
若菜の言葉には応えず、鯉伴は話を変える。
「あぁ…あれ?あれは…『どらむかん』って読むの。あ、もちろん当て字よ?」
うふふ、と若菜は笑った。
『銅鑼夢舘』と書いて『どらむかん』と読むのか——日本語も難しくなったものだと鯉伴は小さく笑った。
若菜がアルバイト先の店『銅鑼夢舘』を出た時、不意に上から声を掛けられた。声のする方へと顔を上げれば屋根の上、見知った男が座っていた。
仕事は終わったかい?——男の声に若菜は微笑んで頷いた。
「これから帰るのかい?」
「えぇ」
「…ちょいと話をしないかい?」
「……。…いいわ」
明日は日曜日だし、と、若菜はほんの少し考えてからそう答えた。
何処か行きたい所があるのなら連れて行ってやらねぇでも無いが、との鯉伴の言葉に、海が見たい、と若菜はリクエストした。
それに鯉伴はひとつ頷いて屋根の上から舞い降りる。
「連れて行ってやる…しっかり、つかまりな」
鯉伴はそう言うと若菜をひょいと抱き上げ、トン、と軽く地を蹴った。
そして今、此処に居る。
「——ね、聞いてる?」
「え?」
「あなたが、あの席に座っていてくれて良かった、って言ったのよ」
また、ぼんやりしてる、と若菜は困った顔をした。
「え?なんで?」
「マスター…私があなたに驚いているのを、あのポスターの所為だと思ってくれたから」
マスターにはあなたが見えなかったみたい、と若菜は思い出す様に呟いた。
あぁ…と鯉伴もまた思い返す。そう言やぁお化け屋敷の張り紙がしてあったっけ?と。
この手のモノは自分が生まれた江戸の時代から無くもないが、科学だなんだとあれからすっかり変わってしまった現代であっても、人そのものはそれ程代わり映えはしていないのだ、と実感する。
「…ねぇ…お化けって信じる?」
幽霊とか、でもいいんだけど、と若菜は問うた。
ん?と鯉伴は視線を投げて返す。
「…お前は信じてんのかい?」
「…人って不思議よね…信じてないかいないくせに、お化け屋敷だとか怪談とか…」
逆に信じていないからかしら——鯉伴の言葉には答えず、若菜は呟いた。
「…オレは…信じるぜ」
ややあって、静かに答えれば、若菜は僅かに表情を曇らせた。
「どうして?」
「…どうしてって、お前…そりゃ…なんだ…」
どうしても何も、自分自身がその類いのモノだからだ——。けれど、それを言える訳も無く。
「もしかして見ちゃったとか?」
「え…あ…まぁ…そんなトコか?」
「…そう…なんだ…。…でも、ね——」
若菜は言葉を切って、ひとつ大きく息をして続けた。
「そういうコトはあんまり言っちゃダメよ」
眉根を寄せる若菜に鯉伴は穏やかに問うた。
「…何か…あったのかい?」
2
「…私の両親は一昨年の冬に亡くなりました。事故だったの」
若菜はポツリポツリと話し始めた。
あの日は私の誕生日で、日曜日だったから朝から家族ででかけたの。映画を見て、買い物をして、食事をして、一日家族で楽しんだわ。
その帰り。それを見たのは。
すっかり暗くなった道を父の運転する車で家に帰る途中だった。
急にね、目の前、フロントガラスのすぐそばくらいだったと思う。何か獣の様なモノが張り付く様に現れたの。
父も母も、そして私もビックリしたわ。ビックリしたなんてモノじゃなかった。
いきなり現れたそれに父はハンドルを奪われて——。
気が付いたら病院だった。そこには父も母も居なくて。
どうして父も母も居ないんだろうって思ったけれど、それもすぐに解った。居なくて当然。父も母も死んでしまっていたんですもの。
父の運転していた車は事故を起こして横転して——そして、私だけ助かった。
それはきっと母が私を抱いて庇ってくれたからかも知れない。
警察は——事故の原因は父の運転ミスだと言った。
違うのに。
だってあの時、私は見たもの。赤い怪し気な瞳をハッキリと覚えてるもの。
私は、父の所為じゃないって、みんなに解ってもらいたくて正直に話したわ。
『本当です、私、見たんです!信じて!』
けれど。
誰も信じてはくれなかった。
『可哀想に…』
それどころか、両親を亡くして正気を無くしたのだと哀れんだ目を向けられてしまった。
「私、あやうく、そういう病棟に移されそうになったの…心の病気だと思われちゃって…」
若菜は小さく笑った。参っちゃった、と。
「幽霊だとかお化けだとか、そういったのを見たとか言っちゃいけないだって。ホントに見たとしても言っちゃったら変な目で見られちゃうって…。だから、あなたもそういった事はあまり言っちゃダメよ?」
「……。…何処で見たんだい?ソレを…」
険しい表情で鯉伴は低く問うた。
「だから、ダメだってば」
「いいから答えな。何処で見た?」
無闇矢鱈に人間に危害を加えている輩が居るのだとしたら放ってはおけない。何処からか流れてきたはぐれ妖怪か?調べる必要がある。
「よく覚えていないわ。夜だったし、車だったし。どの道をどう走っていたかなんて私にはよく解らない…」
頭を振る若菜に、鯉伴は小さく溜め息を付いた。
「なら、ソレはどんなヤツだった?覚えてんだろ?」
若菜は再び頭を振った。もういい、と。
「…なんで?」
「だって、死んだ両親は返って来ないもの。だから…もう、いいの」
「そうはいかねぇんだよ」
「どうして?」
「…どうしてってお前…そりゃ…」
この辺りが奴良組のシマだからだ。そして自分はその総大将だからだ——鯉伴は心中呟いたが、口に出しては何も言わなかった。
「…ありがとう…ございます」
ペコリと若菜は頭を下げた。
「…私の話を、信じて下さって。笑わないで聞いて下さって…どうもありがとうございます」
若菜は微笑んだ。
「なんだか、ちょっとだけ気持ちが楽になりました」
「…オレは…信じるって言わなかったかい?」
懐から煙管を取り出すと火を付けて、ひとつ吹かすと鯉伴は穏やかに笑った。その笑顔に若菜も顔をほころばせる。
『人恋しさと愛しさを履き違えてはいけないよ?』
ふと、『銅鑼夢舘』のマスターの言葉が若菜の脳裏に蘇る。
『君の寂しい気持ちにつけ込む男が居るとも限らない、そういう事だよ』
若菜の瞳が揺れたのは、刻み煙草の煙が目にしみただけではなかった。
-——あぁ、どうしよう。こんな所までついて来ちゃったけど…。でも海見たいって言ったのは私だし。…今更、疑うの、私?…疑う、の…?——
「…どうして…どうして信じてくれるの?」
「どうしてって…。…迷惑かい?」
聞き返せば、若菜はフルフルと頭を振って見せた。そんなんじゃないわ、と。
「——聞きたいかい?」
その理由(わけ)を——。鯉伴は真っ直ぐに若菜を見つめた。
ゴクリ、と固唾を飲んで若菜は頷いた。知りたいです、と。
「…そうさな——」
鯉伴は煙管の火をポンと落として、ひとつ大きく息を吐き出した。
「信じてくれた礼に、話そうか…若菜」
煙管を懐に仕舞い若菜に小さく笑えば、真っ直ぐにこちらを見やる若菜の瞳があった。
「…信じてくれたのは、あなた…の方だわ」
嬉しい事を言ってくれるねぇ——鯉伴は目を細める。
「若菜ぁ…よぅく見てな」
若菜の見ている前で鯉伴の姿が霞んでゆく。そして——消えた。
「…!?」
若菜は目を見開いた。
〝若菜ぁ…オレが見えるかい…?〟
声だけが若菜に届いた。
「…見え…ないわ…。…そこに居るの…?」
〝…お前の目の前に…居る…〟
また、声だけが届いた。
「…どうして…見えない、の…?」
〝…そいつは…〟
何も無かったそこに、朧げに輪郭が見え始める——そしてハッキリと鯉伴の姿が現れた。
「…さっきの答えだ、若菜」
「………」
海が見たいと若菜が言った時、鯉伴は若菜を横抱きにしてひょいと宙を舞った。
——え、なに!?空…を、飛んで…いるの?
——海が見たいんだろ?飛べばすぐだ。
夜風が頬を打つ。七月といっても夜風は昼のそれとは違いひんやりとして。
真下を見やればネオンの下を歩く人々が小さく見えた。
自分は今空を飛んでいる。夢ではなく空を飛んでいるのだと思った時、若菜は怖くなった。思わず鯉伴の首に巻き付けた両腕に力が入る。
ぎゅっと力を込めて抱きつけば、応える様に男の腕が更に力を込めて抱きしめてきた。
怖いかい?と耳元で囁かれた時、沈香の香りがした——。
「…初めて会った時、お前は幽霊と見たと言ったな?…当たらずとも遠からず…だよ」
その時の鯉伴の見せた微笑みが——若菜にはとても寂し気に見えたのだった。
つづく