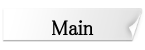小雪春 7 —— 鯉伴 嫁取り物語 ——
1
——半妖?
——そう。半分人間で半分は妖。だから半妖。返せば人間でも妖でもない…半端な存在なんだよ、俺は。
荒唐無稽なカミングアウトだった。
まさか、と思わず口にしそうになったが、鯉伴のその眼がとても嘘を言っている様には見えなかった。
けれど。
信じろと言われても…。やぱり荒唐無稽すぎて若菜は言葉を失ってしまった。
——どうしたらいいんだろう。これから私は、どんな顔をして会えばいいんだろう——
——そこまで考えて、若菜は耳まで赤くする。どんな顔をして会えば
だなんて。私ったら…。
「…ちゃん。若菜ちゃん」
自分を呼ぶ声にようやく気がついて、若菜は我に返った。
「はい!…ご、ごめんなさい。なんでしょう、マスター」
顔を上げれば、カウンターの中から心配げな表情で『銅鑼夢舘』のマスターがこちらを見ている。
「大丈夫?若菜ちゃん。…気慣れない着物で疲れちゃったんじゃない?」
「あ…いえ…。私、着物は全然大丈夫なんです。ちょっと考え事しちゃってて…ごめんなさい」
「なら、いいけど」
最後のコップを洗い終えたマスターは手を拭き乍らカウンターの外へと回る。
「今日はそろそろ閉めようか?」
「え?どうしてです?」
見れば、時計の針はまだ七時前だ。
「だって、今日はお祭りじゃないか。今日くらい早仕舞いしてお祭りに行こう。僕じゃ役不足だとは思うけど、エスコートさせてもらうよ」
その為に今日は浴衣で来てもらったんだよ、とマスターは微笑んだ。
「ごめんね、僕も浴衣だったら良かったんだけど…生憎持っていなくて」
それに着方も解らないし、と、困り顔で笑うマスターはTシャツにGパン姿だ。そんなマスターに若菜も破顔する。
「着物なんて、簡単なんですよ。慣れていないだけだわ、マスター」
神社へと続く石畳の通り、両脇にはびっしりと露店が並んでいる。
若菜はマスターに連れられて、様々な露店を見て楽しんだ。金魚すくいもしたし、的当てもした。
「折角すくった金魚、もらわなくても良かったのかい?」
「うん。私、金魚の育て方が下手みたいで…すぐ死なせちゃうの。一生懸命やってるんだけど…」
可哀想でしょ?だからもらわないの。と、若菜は小さく笑った。
そんな若菜を見てマスターは、そっか、とだけ答えた。
「ね、若菜ちゃん。占いだって。やってみない?」
マスターが指差す先を見れば『手相』の文字。若菜は、うんとニッコリ頷いた。
先に若菜が見てもらう事になった。
占い師は温厚な白髪の男であった。占い師は、それでは失礼、と若菜の白い手を取りうむうむと唸った。
「お嬢さん、あんた、近いうち結婚するようじゃの。手相にそう出ておる」
さてはいい人がいるのじゃな、と占い師は笑った。
「マスターったら、私だけ見てもらっちゃって良かったの?」
リンゴ飴をかじり乍ら若菜は問うた。
露店の建ち並ぶ通りから、少し外れた所にあるベンチにマスターと若菜は腰掛けていた。もう目の前が神社だ。
いいんだよ、とマスターは笑う。
「夏休みが終わったら二学期だね」
「うん」
「そろそろ、進路指導があるんじゃないの?」
「うん」
「進学するの?」
「ううん」
若菜は眼を伏せて、ゆるゆると頭を振った。
「そんなお金に余裕も無いし…それに」
「それに?」
マスターはチラリと若菜に視線をやる。
「勉強したい事があって…京都に行こうと思っているの」
友禅染の勉強をしたいのだと、若菜は言った。
「だから、学校卒業したら、あの家を売ってお金に変えて、京都に行くの。そこで小さなアパート借りて…頑張ろうかなって」
「友禅なら、東京でも勉強できるじゃないか」
なにも京都になんか行かなくたって…。と、マスターは身体ごと若菜に向き直った。
「…でも…」
「若菜ちゃん!」
マスターは若菜の手を取った。
「…は…い…」
まちくり、と若菜は瞬きする。
あ、ゴメンね、とマスターは若菜の手を放した。
「…ねぇ、若菜ちゃん…京都になんか行かないで欲しい。卒業してもウチの店で働いて欲しい。お給料だってきちんと払うよ。アルバイトじゃなくて正社員としてだ」
マスターは膝の上においた両の手をぎゅうっと握りしめた。
「思いつきで言ってるんじゃないんだよ。ウチのお客さんは若菜ちゃん目当てで来る人も多いし…」
けど、それだけじゃない。ずっと胸に秘めてきた、君の事。
「…僕と君はちょっと年が離れてるけど…でも、本気なんだよ。…ずっと君を見てきた…」
若菜は大きく眼を見開いた。何という展開だろうか。思いもよらなかった。
「えっと…マスター、私…。…あの…えっと…」
若菜は俯いた。
「さっき、占いで近いうち結婚するって言われたよね。…その相手、僕じゃダメ…かな?」
「え?」
若菜は顔を上げてマスターを見返した。
「僕も最初は占ってもらうつもりしてたんだよ。だけど、君の占い聞いてて…僕も同じ様な…その、結婚近いって出たら、もう舞い上がっちゃいそうで…」
頭の後ろをポリポリとかいてマスターは笑った。暗くてよく見えないが、きっとその顔は真っ赤なのだろう。
えっと——若菜は両手を膝の上に置いて、持っていたかじりかけのリンゴ飴の軸を左へ右へと回していた。小さくかじった痕がくるりくるりと回った。
2
「ね、若菜ちゃん!友禅染もいいけど、その前に僕の事を考えてはもらえないかな!?」
マスターの手が若菜の手を包む。くるくると回っていたリンゴ飴は動きを止める。
「…マスター…私…」
ごめんなさい、と、若菜は蚊の鳴くような声で言った。
「…ずっと考えてきた将来の夢なの。私、着物好きだし…一生着物に関わってゆけたらなぁとか…」
「だから!東京だって友禅染の勉強はできるじゃないか!」
ポタリ。リンゴ飴は若菜の手から滑り落ちて、若菜の足元、地面に転がった。
その時——。
すぅっと闇から細長いモノが現れて、マスターの喉元に添えられる。
「…?…」
マスターはピクリと身体を震わせる。ピタリと触れた感触が冷たかったからだ。
それは、一本の煙管だった。
〝…いけねぇなぁ…無理強いしちゃあ…〟
闇の中から声がして、やがて闇の一部が揺らいだ。
「…鯉…伴さん…?」
若菜の目の前、マスターの背後に姿を現したのは、その喉元に煙管を突きつけた奴良鯉伴、その人だった。
「お前は…誰だ!?」
マスターは眼だけを動かして背後を伺う。ゴクリと生唾を呑んだ。闇の中からいきなり現れたのだ。驚くなという方が無理だろう。
「…俺かい?…俺は…そうさな…妖怪?」
鯉伴はニヤリと笑った。
「人間ってヤツは恐ろしいねぇ…。『君の寂しい気持ちにつけ込む男が居るとも限らない』そいつは…他でもねぇ、お前さんの事じゃねぇのかい?」
囁く様にそう言って、すぅっと消えてゆく。そして、今度はマスターの目の前、若菜を背に庇う様に現れる。
「うわっ!?」
のけ反るマスター。その瞳は恐怖していた。
「…そして、器も小せぇときたもんだ。若菜はまだお前のモンじゃねぇだろう?それともナニかい?もう…手ぇ付けたのかい?」
鯉伴は片頬で笑う。が、その瞳は笑ってはいなかった。金の瞳が妖しく光る。
「女口説くのに、いきなり女の夢砕くってのは頂けねぇな…。俺だったら、叶えてやるがねぇ…」
妖怪の寿命は半端ではない。十年や二十年、屁でもないのだ。
「…う…うわぁっ!?」
マスターは座っていたベンチから転がり落ちた。地べたに尻餅をつく。
「…く…来るな、化け物!」
「……。…失敬な。誰が化け物だ。俺は半妖。半分はあんたとおんなじ人間なんだぜ?」
やれやれ、と鯉伴は困った様に笑う。
声にならない声を上げて、マスターは走り去って行った。
「あ、まって、マスター!?」
走り去る男の背中に手を伸ばす若菜を鯉伴は制した。止めておけ、と。
「…ずっと…聞いていたの…?」
「…あ?…まぁ…」
鯉伴は言葉を濁した。
「着物姿…初めて会った時以来だな」
あれは、初めて会ったとは言わねぇか、と鯉伴は笑う。
「…ううん…初めて会った時だわ…」
若菜は微笑んだ。
「よく似合ってるぜ」
「ありがとう」
「…京友禅、勉強したいんだって?」
「…はい…」
そうかい、と鯉伴は小さく笑った。
「京都は…いい街だぜ…」
「…ウチまで、送ってやる…」
鯉伴は若菜に手を差し伸べた。
3
「おまたせ」
鯉伴が振り返ると、スイカの乗った盆を持った若菜が立っていた。
あれから若菜は鯉伴の腕に抱かれて空を飛んだ。空を飛んだのは二回目だった。空の上から見る露店の明かりはとても綺麗で、空を飛ぶ二人の世界は文字通り二人きりの世界となった。
誰も見ていない。誰も邪魔しない。
若菜の家の前に降り立った時、若菜は鯉伴に微笑んで言った。——一緒に花火をしませんか、と。
「よく冷えてるわ。さぁ、どうぞ」
お塩もね、と若菜は盆をそこへと置いた。
ここは若菜の家の一階の和室。その和室のサッシを開け放つと、小さい庭に出る事ができる。
そこで鯉伴は胡座をかいて、まあるい月を仰ぎ見ていた。
「…スイカに塩…かけんのかい?」
「そうよ?あら、かけないの?」
そんなもの、かけた事がない、と鯉伴が言えば、若菜は食卓塩の蓋を取って、盆の上のスイカのひとつにひとふりした。
「塩を少しふると、甘みが増すのよ?食べてみて?」
庭には水の入ったバケツがひとつ。その横に、小さなろうそくがひとつ。小さな火を灯していた。
若菜は線香花火に火を付けて、それをじっと見つめていた。松葉を思わせる様な仄かなオレンジ色が目に優しい。
「…私、花火は、線香花火が一番大好き」
「…俺も…好きだ…。お袋も好きだった…」
「そう…」
「この花火は…江戸の時代から変わらねぇな…」
呟く様に鯉伴が言えば、若菜が持っていた線香花火の先から濃いオレンジ色の玉がポタリと落ちた。
「…やっぱり、本当なんですね…」
「何度も言わせるなよ。…俺は半妖…もう四百年も生きてる…江戸の時代から、明治、大正、昭和、平成…と見てきた」
鯉伴は新しい線香花火に火を付けて、若菜に差し出す。
ありがとう、と若菜はそれを受け取って、またオレンジの光を見つめた。
「…でも…私、あなたが妖怪って思えなくって…そんなカンジ全然しなくって…」
自分の目には自分と同じ人に見えると若菜は鯉伴に視線を向ける。
そんな若菜の言葉を受けて、鯉伴は小さく笑う。
「そいつは…おまえが人間だからだ」
鯉伴も線香花火に火を付けて、それを眺める。
「…俺ぁ…半妖だから、自分の中に人である自分と妖である自分が居る…」
それが対峙する相手によって強く出る自分が異なるのだと鯉伴は言った。
「?」
意味が分からず、首を傾げる若菜。線香花火の淡いオレンジ色に照らされる、そんな若菜の顔を見やって鯉伴は笑う。
「つまり…人と関われば俺の中の人の部分が強く表に出ちまうし、妖どもと関わってる時は妖の部分が強く出る…」
若菜の目に自分が人としてうつるのは、それは若菜が人であるからに他ならないのだ、と鯉伴は説明する。
「…ややこしいだろう?」
クスリと鯉伴は笑った。
「あなたは…どちらでありたいと思ってるの?」
「…?…」
またひとつ線香花火のオレンジ色の玉がポタリと落ちて、小さなろうそく一本の明かりだけとなった。
鯉伴はろうそくに線香花火を添えて火を付ける。そしてそれを若菜に渡した。
「人でありたいの?それとも…妖…?」
若菜は線香花火から鯉伴に視線を移す。
「………。…俺は…」
妖として生きると決めた。もう随分と昔に。そしてそうして今まで生きてきた。
そう、と若菜は線香花火に視線を戻した。
——妖として生きると決めた。
自分は人間。妖怪とは相容れない存在。——そう言う事だ。若菜は大きく息を付いて顔を上げる。
けれど、鯉伴の顔を見た途端。
ポロポロポロ。若菜の瞳から大粒の涙が溢れた。
「!?…若…菜…?」
なぜ泣く?鯉伴は眉を潜めた。
「あ…あれ…。…なに、これ…。…なに、泣いてるんだろ…私…」
まだ火の付いている線香花火を手から放して、溢れる涙を懸命に拭う。
地面に落ちた線香花火はそのまま松葉の様なオレンジ色を放ち続けた。
——私、何を期待してたんだろう…バカみたい――
鯉伴は、この時、若菜の涙の意味を計りかねていた。
「…夢…あるんだろう?京の友禅染…。…頑張りな…」
鯉伴は燃え尽きた線香花火を手から放して、涙に濡れた若菜の頬にその手を伸ばす。親指の腹で涙を拭った。
「…う…うん…」
若菜は眼を伏せて頬に添えられた鯉伴の手に自分の手を重ねた。
温かい手だった。
これが妖怪の手なのかしら。若菜は思う。——これは…人の手だわ。
つづく