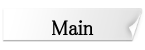四方山話 其の三 —— 拍手用小話 ——
1
鯉伴がうっかり(?)帰って来て早数ヶ月が経とうとしていた。
その間、奴良組本家は平和そのもの。何も無かった。
たまに出入りはあるにはあったが。
リクオの跡目について『京都から帰ったら三代目襲名』となってはいたが、二代目が生きていたとあっては、さて、どうしたものか。
少々事情がややこしくなってしまった。
奴良組本家の妖怪達も口には出さないが、皆困惑していた。
けれど、そんな皆の思惑を知ってか知らずか、鯉伴は飄々と言ってのけたのだった。
「リクオが三代目襲名だってねぇ。そいつは目出てぇ!」
鯉伴は隠居する気満々だったのである。
そんな父の反応にリクオは眉をひそめた。
「そんなに簡単に手放していいの?総大将ってそんなに軽いの?」
しかし。
鯉伴にとっては軽いとか重いとかの問題ではなかったのだ。
『何百年も総大将としてこの組を守ってきたんだ。もういいだろう?』
素直な本音である。
奴良組総大将の座は、あっさりと明け渡されてしまい、リクオは否応無しにそこへ座らされてしまった。
なにはともあれ三代目襲名は滞り無くとり行われ——。
そうして今、鯉伴は悠々自適な隠居生活を満喫していた。
しかし、夢にまで見た隠居生活はあまりにも退屈であった。
まったくもってする事が何も無い始末。これでは忙しく総大将をやっていた時の方がいくらかマシだ。
かといって、今更リクオに総大将の座を返してくれとも言えない。
ま、言いたくもないが。
とにかく退屈な毎日であった。
あまりに退屈なので、一度リクオの学校とやらへついて行った事がある。さぞかし楽しい所なのだろうと思っていたら、これまたすこぶる退屈な場所であった。
周りに気付かれる事の無い様に畏れを放ち、上手くやってのけた筈だったが、リクオにはしっかりとバレていた。
おまけに『父兄参観じゃないんだから、やめてよね!』と怒られてしまった。
「父兄参観っていうのはね、子供の学校へ親が出向いて行って子供の勉強するさまを見ることよ」
そう若菜に教えてもらったのは、それから何日も経った日の事。
とにかく退屈で、こんな退屈な毎日を父•ぬらりひょんはどうやって過ごしているのだろうかと疑問に思ったが聞く気にもなれず、現在に至っている。
聞いた所でまともな応えなど返って来ない事は、今までの経験から充分に理解出来たからだ。
そして今日も暇な一日をぼんやりと過ごしている。
——はやく若菜の用事が終わらねぇかなぁ——
若菜は忙しい。朝から晩まで家事に追われている。自分では到底手助けになどならず——うっかり手助けなどしようものなら、『二代目にそのような事をさせるわけには!』と、毛倡妓達が大騒ぎをしてしまう。
退屈なんだよ、解ってくれ——けれど、そんな鯉伴の心の小さな叫びは誰にも届かなかったのである。
「あなた、あなた、あなた!」
自分を呼ぶ声に顔を上げれば、こちらにかけて来る若菜の姿が見えた。空になった大きなカゴを手にさげている。どうやら洗濯物を干し終えたらしい。
「どうした、若菜?」
若菜の好きな笑顔を作ってみせて鯉伴は答えた。
2
「…これなのよ…なにかしら?」
夫を見つけた若菜は洗濯カゴを放り出して、夫の手を引いた。
そして今二人してそれを見ている。
「…なんだい、こりゃ?」
「私が聞いてるんです!」
もう!っと若菜は鯉伴の腕をつねった。
「痛ぇな…。…こんな所に——」
「うわっ!なに、このホコラ!?」
後ろから声がして鯉伴と若菜、二人して振り返ればそこにリクオが立っていた。
「あら、お帰りなさいリクオ」
笑顔の母に、これまた笑顔を返してリクオは父に向き直る。
「なに、これ?ボク、こんなの初めて見た。っていうかこんな所にホコラなんかあったんだ…」
そこには小さなホコラがあった。ボロボロで、今にも朽ち果ててしまいそうである。
奴良組本家の庭の隅っこに若菜が見つけた怪し気な古びた小さなホコラ。
この屋敷自体が怪し気なシロモノなので、その敷地内に怪し気なモノのひとつやふたつ見つかった所で驚く事も無いのだが——。
「…俺に聞くなって…」
面倒臭そうに頭をかく鯉伴にリクオは、知らないの?と怪訝そうな顔をした。
「知る訳ねぇだろ?」
「なんで?」
「なんでってお前…俺はこの家にはブランクがあるからな…」
——出た、困った時の『ブランク』だ——
一瞬ムッとするリクオだったが、父に聞いた自分が悪いのだと思い直した。こういう事は爺ちゃんに聞くのが一番なのだ。
が、しかし、頼みの祖父が今ここには居なかった。数日前からふらりと何処かへ出かけてしまった。いつ返ってくるかも見当がつかない。
「とにかく、三代目、なんとかしやがれ」
「えぇ!?」
父の冷たい言葉にリクオは思わず仰け反るが、しかし今、奴良組本家の総大将は他でもない自分なのである。自分が解決しなければならないのだと、リクオはそのホコラへと向き直った。
そして、その観音開きの戸に手を伸ばした。
「!?」
3
その戸はリクオが手を伸ばす前にゆっくりと僅かに開いた。
ピクリと身体を震わせて、リクオは伸ばした手を引っ込めた。
それは驚いたからではなく、妖気とはまた違う何かを感じたからだった。
見れば、僅かに開いた戸の奥からこちらを伺う黒い瞳があった。
それはパチクリと瞬きを数回繰り返した。そして戸はさらに押し開かれて——出てきたそれは。
出てきたそれは、小さな小さな少女であった。
まるで小人の様な小さい姿。淡い桜色の着物をその身に纏っていた。
「君は…誰——妖なのか?」
リクオの問いに、ホコラから姿を現した少女はほんの少し唇を動かしかけたがすぐに閉ざしてしまった。
「怖くないよ。ボクは君の味方だ。怖がらないで…」
リクオはそうっと声をかける。
「まぁ、可愛らしい…まるで妖精のようね」
若菜が微笑んだ。
母の言葉に、そうだね、とリクオは頷いた。
ふと母に視線をやれば、視界の隅っこに入ってしまう、母の隣にいる父の顔。
——なんて顔してんの…お父さん…——
鯉伴のその表情は、大げさに引きつていた。
「あなた?」
リクオの視線に若菜も夫に目を向ける。
しかし。
鯉伴は何も答えず、ただただ、そのホコラの少女に目を奪われていたのであった。
ホコラから出てきた小人の様な少女も、やがて鯉伴の視線に気付き視線を返した。
「!?」
少女の漆黒の瞳が大きく見開かれ、その顔(かんばせ)にみるみる笑顔が広がってゆく。
「鯉伴!」
その少女はホコラから駆け出した。
「!?あぶねぇ!」
思わず両手を差し出して少女を受け止める鯉伴。鯉伴の手にのる少女はまるでおやゆび姫の様であった。
「鯉伴!鯉伴なのですね!?あぁ、何という奇跡でしょう!」
鯉伴の手の上の小さな少女は、その黒真珠の様な目からポロポロと大粒の涙をこぼした。
——げっ…もしかして、お父さんの昔の女とかっていうんじゃ…——
そんな考えがリクオの脳裏をよぎった。
父は確かにいい男かも知れない。本人にその気が無くても、周りの女が放っておかないかも知れない。それに父は…かくる400を越えている。
——女の一人や二人居たって…おかしくないじゃないか——
リクオの想像は悪い方、悪い方へと傾いていった。
しかし、そこまで考えてリクオはハッとなって母•若菜に視線を投げた。
若菜は——瞬きひとつせず、夫とその手の上の少女を見つめていた。
きっと母も同じ気持ちに違いないのだ——リクオはそう感じた。
「鯉伴、ここは何処です?ここは一体——」
「奴良組本家だ…お袋…」
手の平の上の少女に鯉伴は穏やかに答えた。
——なんだ「女」じゃなくって「お袋」だったんだ…って…えぇっ!?——
なんか、わけ解らなくなってきたよ、爺ちゃん早く帰ってきてっ!——リクオは目の前の父と、父の手の平に乗る少女を見ながら心の中で叫んでいた。
鯉伴だけでなく、その母までもが復活(しかもミニマム!)してしまった。さて、どうなる、奴良組!?どうするリクオ!?
つづく